山里ぽん太
Volume Trek
30 September 2018

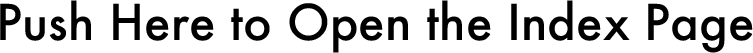
山里ぽん太Volume Trek30 September 2018 |
山里ぽん太はVolumeをトレッキングしました。 |
 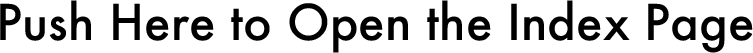 |
|
Chapter 1 ぼりゅーむ |
|
Volume , the fine frontier . These are the voyages of the stareship Ponterprise . ぼりゅーむの知識がないので、とっかかりに、シェルフツールを見てみましょう。 シェルフ・ツールで、Volume が出てきそうなタブは、「Volume」と「Cloud FX」です。 「Volume」タブを開くとこんなことになっています。  「Cloud FX」タブを開くとこんなことになっています。  というわけで、順番に押してみましょう。 |
|
Chapter 2 Volume |
|
というわけで、まずは、「Volume」タブの「Volume」です。 リファレンスの「Volume」リンクを開くと、「IsoOffset geometry node」のページが開きます。  ということで、Houdini でボックスを作って、シェルフツールの「Volume」ボタンを押してみましょう。 ありゃりゃ、なーんと、「converttofog」ノードが追加されるではあーりませんか(笑)。  というわけで、箱が霧になりましたー。  適当なセットを組んでレンダリングしてみました。 なんと、レンダリングされました!。  霧の表現なので、光をいろいろ工夫すると、いろんな表現ができそうです。 ががががが、しかし、それは次の機会に譲ることにします。 ここは、ここまでにして、次行ってみましょー。 |
|
Chapter 3 SDF Polys |
|
次は、「Volume」タブの「SDF Polys」です。 リファレンスの「SDF Polys」リンクを開くと、「VDB from Polygons geometry node」のページが開きます。  「VDB」って何でしょう?(謎)。 ググってみたら、こんなページがヒットしました。 「OpenVDB」なのだそうです。 よくわかりませんが、先に進みます(謎)。 ということで、Houdini でボックスを作って、シェルフツールの「SDF Polys」ボタンを押してみましょう。 「vdbfrompolygons」ノードが追加されました。  霧の箱の周囲が黒いんですけど?。  レンダリングしたらこうなりました。 霧がデカイです(笑)。  |
|
Chapter 4 SDF Particles |
|
次は、「Volume」タブの「SDF Particles」です。 リファレンスの「SDF Particles」リンクを開くと、「VDB from Polygons geometry node」のページが開きます。  シェルフツールの「SDF Particles」ボタンを押すと、「vdbfromparticles」ノードが追加されました。  でっかい球体ができました。 これはアレです。 ポイントに球体が作られているようです。 「Copy to Points」みたいな感じです。  レンダリングしたらこうなりました。 よくわかりません(謎)。 隣に置いた箱が隠れてしまいそうだったので、赤い色をつけてみました。  |
|
Chapter 5 Paint Color Volume |
|
次は、「Volume」タブの「Paint Color Volume」です。 リファレンスの「Paint Color Volume」リンクを開くと、「Paint Color Volume geometry node」のページが開きます。  シェルフツールの「Paint Color Volume」ボタンを押すと、「paintcolorvolume」ノードが追加されました。  でもって、こんなメッセージが出ます。  で、マウスで、お絵かきしてみました。  レンダリングしたらこうなりました。  パラメータをいじって色をつけてみました。  これを使うと、もしかしたら、虹が描けるでしょうか?。 とりあえず、置いといて、先に進みましょう(笑)。 |
|
Chapter 6 Paint Fog Volume |
|
次は、「Volume」タブの「Paint Fog Volume」です。 リファレンスの「Paint Fog Volume」リンクを開くと、「Paint Fog Volume geometry node」のページが開きます。  シェルフツールの「Paint Fog Volume」ボタンを押すと、「paintfogvolume」ノードが追加されました。  で、メッセージが出ます。  で、マウスで、お絵かきしてみました。  レンダリングしたらこうなりました。  パラメータをいじって色をつけようとしましたが、色はつきませんでした。 Fog だからでしょうか?。 確かに、霧に色がついていたら、不気味だと思いますが(笑)。 とりあえず先に進みます(謎)。  |
|
Chapter 7 Paint SDF Volume |
|
次は、「Volume」タブの「Paint SDF Volume」です。 「SDF」とは、アレです。 「Signed Distance Field」です。 日本語に訳すと「符号付き距離場」となるでしょうか?。 というわけで、リファレンスの「Paint SDF Volume」リンクを開くと、「Paint SDF Volume geometry node」のページが開きます。  シェルフツールの「Paint SDF Volume」ボタンを押すと、「paintsdfvolume」ノードが追加されます。  で、メッセージが出ます。  で、マウスで、お絵かきしてみました。  レンダリングしたらこうなりました。 お絵かきしたのに、四角いです(変)。  パラメータをいじって色をつけようとしましたが、色はつきませんでした。 SDF は、形状ではなくて、数学の分布を表現する数字の集まり、ってことなのでしょうか?。  というわけで、先へ行きます(笑)。 |
|
Chapter 8 Fog Points |
|
次は、「Volume」タブの「Fog Points」です。 というわけで、リファレンスの「Fog Points」リンクを開くと、「Volume Rasterize Points geometry node」のページが開きます。  シェルフツールの「Fog Points」ボタンを押すと、「vdb」ノードと「volumerasterizepoints」ノードが追加されます。  で、こんなんなります。  レンダリングしたらこうなりました。 ポイントに Fog を Copy to Points するみたいな感じかな、と思います。  |
|
Chapter 9 Fog Particles |
|
次は、「Volume」タブの「Fog Particles」です。 というわけで、リファレンスの「Fog Particles」リンクを開くと、「Volume Rasterize Particles geometry node」のページが開きます。  シェルフツールの「Fog Particles」ボタンを押すと、「vdb」ノードと「attribwrangle」ノードと「volumerasterizeparticles」ノードが追加されます。  で、こんなんなります。  レンダリングしたらこうなります。 やはり、ポイントに Fog を Copy to Points するみたいな感じのようですが、「Fog Points」よりも、さらによりいっそう、ぼんやりしています。  |
|
Chapter 10 Fog Curve |
|
次は、「Volume」タブの「Fog Curve」です。 というわけで、リファレンスの「Fog Curve」リンクを開くと、「Volume Rasterize Curve geometry node」のページが開きます。  シェルフツールの「Fog Curve」ボタンを押すと、「volumerasterizecurve」ノードが追加されます。  で、こんなんなります。  レンダリングしたらこうなります。 これはカーブに基づいてボリュームを配置するみたいなので、面の真ん中がへこんでいる、ってことなのでしょうね。  立方体じゃつまんなかったかもしれないけれど、どんどん行きます(笑)。 |
|
Chapter 11 Convert VDB |
|
「Volume」タブの最後は「Convert VDB」です。 というわけで、リファレンスの「Convert VDB」リンクを開くと、「Convert VDB geometry node」のページが開きます。  このノードは、Volume の型を変換するノードみたいなので、さらっ、と流して、次行きます(笑)。 |
|
Chapter 12 Cloud Rig |
|
というわけで、次は「Cloud FX」タブの「Cloud Rig」です。 リファレンスの「Cloud Rig」リンクを開くと、「Cloud Rig shelf tool」のページが開きます。 ジオメトリノードじゃなくて、シェルフツールです。  というわけで、Houdini の「Cloud Rig」ボタンを押したら、こんなことになりました。  「cloud_from_cloud_rig」ノードと「sunlight」ノードと「skylight」ノードが追加されています。  「cloud_from_cloud_rig」ノードの中にダイブすると、こんなことになっています。  レンダリングしてみると、こんなのです。 雲です。 Fog とは感じが違います。  |
|
Chapter 13 Cloud |
|
というわけで、次は「Cloud FX」タブの「Cloud」です。 リファレンスの「Cloud」リンクを開くと、「Cloud geometry node」のページが開きます。  Houdini の「Cloud」ボタンを押したら「Cloud」ノードが追加されました。  シーンビューはこんな感じです。  レンダリングしてみると、こんなのです。 なんか、蜜豆の寒天みたいです(笑)。  |
|
Chapter 14 Cloud Noise |
|
というわけで、次は「Cloud FX」タブの「Cloud Noise」です。 リファレンスの「Cloud Noise」リンクを開くと、「Cloud Noise geometry node」のページが開きます。  「雲のようなノイズをFogボリュームに適用します。」とのことなので、Chapter 13 の結果に、コイツを適用しましょう。 というわけで、Houdini の「Cloud Noise」ボタンを押したらこんなんなりました。  「cloudnoise」ノードが追加されています。  レンダリングしてみると、こうなりました。 蜜豆の寒天が、もくもくの雲になりました。  |
|
Chapter 15 Cloud Light |
|
というわけで、次は「Cloud FX」タブの「Cloud Light」です。 リファレンスの「Cloud Light」リンクを開くと、「Cloud Light geometry node」のページが開きます。  これも、Chapter 13 の結果に適用してみました。 というわけで、Houdini の「Cloud Light」ボタンを押したらこんなんなりました。  「sunlight」ノードと「skylight」ノードが追加されています。  「Cloud_Light」ノードの中にダイブすると、こんなことになっています。 「cloudlight_light_points」という名前がついた「Object Merge」ノードと、「cloudlight」ノードが追加されています。  レンダリングしてみました。 写りません。!! よくわかりません(謎)。 先に進みます(笑)。  |
|
Chapter 16 Sky |
|
というわけで、次は「Cloud FX」タブの「Sky」です。 リファレンスの「Sky」リンクを開くと、「Sky geometry node」のページが開きます。  というわけで、Houdini の「Sky」ボタンを押したらこんなんなりました。  「sky」ノードが追加されています。  レンダリングしてみました。  クローズアップして、青空の背景を追加してレンダリングしてみました。  mantra 君に出力してもらいました。  ponticle20180718で空を作ったときは、シェルフツールのボタンを押すことしかできませんでしたが、今はすこしちょっとほんのちょっぴり進歩したかな、と思います。 人類にとっては小さな進歩かもしれませんが、僕にとっては偉大な進歩です(笑)。 |
|
Chapter 16 メモ |
|
① Volume について勉強しようと思って、リファレンスのVolumeのページを眺めてみましたが、簡単ではありません。わからないです。数学的なモデルみたいなものがわかって、その数値にアクセスできると、いろいろ使えそうです。反面、Pyro などでは、Volume を自由自在に操っているわけですが、Pyro の DOP ネットワークを調べると、少しはわかるのかもしれません。今後の課題です。 ② Photoshop などで2Dのお絵かきをする場面で、エアブラシを使う代わりに、Volume を使うことができるかもしれないと思います。 ③ 作ってみた雲は、もくもくの雲でしたが、雲にはいろんな雲があります。雲の表現をどうするか、Volume の応用、ということで、いろいろ考えてみたいと思います。 ④ SDF や VDB など、要素となっている技術の詳細を知りたいものです。おそらく、そんなに難しいことはやっていなくて、僕の赤点頭脳でも十分イメージできるものだろうとは思うのですが。 |